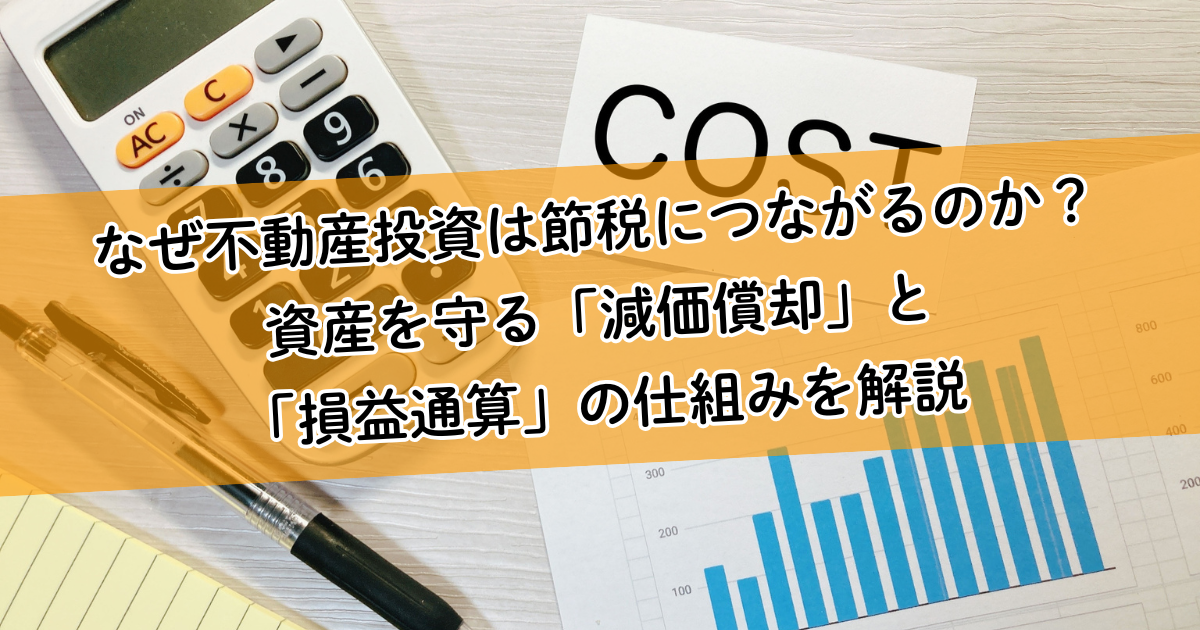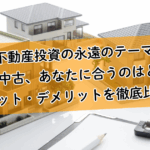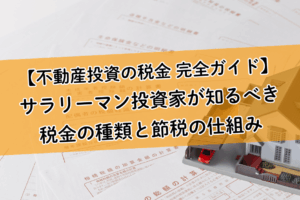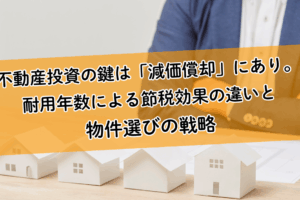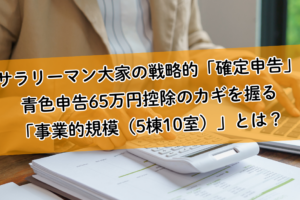「不動産投資はサラリーマンの節税対策になる」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、不動産投資が持つユニークな会計上の仕組みを利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があるためです。しかし、この「節税」の仕組みを正しく理解せずに始めてしまうと、「思ったより効果がなかった」「かえって損をしてしまった」ということにもなりかねません。
今回は、不動産投資による節税の「減価償却」と「損益通算」という主要なからくりを詳しく解説し、さらに資産運用で失敗しないための重要な注意点をご紹介します。
|
この記事がおすすめな人
|
Contents
目次
- 不動産投資における節税の核「減価償却」と「損益通算」の仕組み
- 節税効果は誰が、どのくらい得やすい?具体的なシミュレーション
- 必ず知っておくべき!不動産投資の節税における3つの注意点
- まとめ:節税はあくまで「副産物」。本質は資産運用にあり
不動産投資における節税の核「減価償却」と「損益通算」の仕組み
不動産投資で節税を理解する上で、絶対に欠かせないのが「減価償却」と「損益通算」という2つのキーワードです。
節税のキホン①:お金は出ていかない魔法の経費「減価償却」
車やパソコンが年々古くなって価値が下がっていくように、不動産投資における建物も、年月の経過と共に価値が減少していくと考えられています。この価値の減少分を、法律で定められた年数(法定耐用年数)にわたって、毎年経費として計上することを「減価償却」と言います。
減価償却費の最大の特徴は、実際にお金の支出はないのに、帳簿上の経費として計上できる点です。
例えば、家賃収入が年間500万円あっても、減価償却費として200万円を経費計上できれば、課税対象となる不動産所得を300万円に圧縮できます。実際には懐から200万円が出ていったわけではないのに、税金の計算上は経費として扱える、非常に強力な経費なのです。
| 建物の構造 | 法定耐用年数 |
| 木造(W造) | 22年 |
| 軽量鉄骨造(S造) | 19年~34年(骨格材の厚みによる) |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 |
(※事業用の建物の場合)
節税のキホン②:赤字を給与と合算する「損益通算」
不動産投資の年間の収支を計算した結果、家賃収入よりも経費(減価償却費を含む)が多くなり、帳簿上が「赤字」になることがあります。
この不動産所得の赤字を、給与所得など他の黒字の所得と合算することを「損益通算」と言います。
例えば、給与所得が700万円あるサラリーマンが、不動産投資で200万円の赤字を出した場合、損益通算を行うことでその年の課税対象となる所得を「700万円 – 200万円 = 500万円」にまで減らすことができます。
課税所得が減ることで、納めるべき所得税や住民税も安くなります。サラリーマンの場合、税金は給与から天引き(源泉徴収)されているため、確定申告を行うことで、払い過ぎていた税金が還付金として戻ってくるのです。
これが、不動産投資が節税につながる基本的な仕組みです。
節税効果は誰が、どのくらい得やすい?具体的なシミュレーション

この節税の仕組みから、どのような人が、どのくらいの効果を得やすいのかを見てみましょう。特に効果を実感しやすいのは、高所得のサラリーマンです。
その理由は、日本の所得税が、所得が高ければ高いほど、より高い税率が課される「累進課税」だからです。適用される税率が高い高所得者ほど、同じ赤字額を損益通算しても、より大きな金額の税金が戻ってきます。
【具体例】年収700万円のAさんの節税シミュレーション
言葉だけでは分かりにくいので、簡単なモデルケースで見てみましょう。
- Aさん: 会社員、課税所得700万円
- 購入物件: 中古木造アパート
- 年間の家賃収入: 300万円
- 年間の経費(ローン金利、管理費、固定資産税など): 150万円
- 年間の減価償却費: 200万円
① 不動産所得の計算
家賃収入 300万円 – (経費 150万円 + 減価償却費 200万円) = ▲50万円(赤字)
※手元のキャッシュは「300万円 – 150万円 = 150万円」の黒字ですが、帳簿上は赤字になります。
② 損益通算
給与所得 700万円 + 不動産所得 ▲50万円 = 課税所得 650万円
③ 節税効果
損益通算により、Aさんの課税所得は700万円から650万円に圧縮されました。
所得税率が20%の場合、単純計算で「50万円 × 20% = 10万円」分の所得税が安くなり、これに住民税の軽減分も加わります。
|
課税される所得金額 |
所得税率 |
|
195万円以下 |
5% |
|
195万円超 330万円以下 |
10% |
|
330万円超 695万円以下 |
20% |
|
695万円超 900万円以下 |
23% |
|
900万円超 1,800万円以下 |
33% |
|
1,800万円超 4,000万円以下 |
40% |
|
4,000万円超 |
45% |
(2025年9月時点の所得税率)
必ず知っておくべき!不動産投資の節税における3つの注意点
この仕組みだけを見ると良いことずくめのようですが、大きな落とし穴も存在します。節税という言葉に踊らされず、以下の注意点を必ず理解してください。
注意点1:節税目的で「儲からない物件」を買わない
最も重要なことです。不動産投資の本来の目的は、節税ではなく、家賃収入によって長期的に安定した資産を築くことです。節税効果を過度に重視するあまり、入居者が見つからない、資産価値の低い物件を購入してしまっては本末転倒です。あくまで不動産という事業で利益を出すことが大前提です。
注意点2:節税効果は永続しない(デッドクロス)
減価償却には法定耐用年数という期限があります。例えば木造なら22年で償却期間が終わります。すると、これまで経費として計上できていた減価償却費がなくなり、帳簿上の利益が急増。結果として税金の負担が一気に重くなるタイミングが訪れます。 これを「デッドクロス」と呼び、対策を考えておかないと資金繰りが悪化する危険性があります。
注意点3:売却時にも税金がかかる
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」がかかります。この税率は物件の所有期間によって大きく異なり、5年以下の短期所有の場合は税率が約39%と非常に高くなります。節税目的で短期間に売買を繰り返すのは得策ではありません。
まとめ:節税はあくまで「副産物」。本質は資産運用にあり
不動産投資における節税は、「減価償却」で帳簿上の赤字を作り出し、「損益通算」によって給与所得などと合算することで、課税所得を圧縮する仕組みです。特に所得が高い方ほど、税率が高いため、その効果は大きくなります。
しかし、これは不動産投資という資産運用から得られる副次的なメリットに過ぎません。 本当の目的は、優良な不動産を所有し、安定した家賃収入を得て、あなたの資産を着実に増やしていくことです。節税の知識は、その目的を達成するための有効なツールの一つとして正しく活用しましょう。
税金の話は非常に複雑で、個人の状況によって大きく異なります。具体的な投資プランを立てる際には、必ず税理士などの専門家や、税務に詳しい不動産会社に相談することをおすすめします。